√完了しました! おどりこそう 173666-オドリコソウ ヒメオドリコソウ 違い
すずしろそう きくざき いちりんそう じろぼう えんごさく ふっきそう つくしきけまん;ヒメオドリコソウの花 里山の主役 ヒメオドリコソウは里山の空き地や畔などで主役を張っている。 畑の畔に咲くヒメオドリコソウに種類の違う桜の並木がきれい。おどりこ‐そう〔をどりこサウ〕踊子草 シソ科 の 多年草 。 山野 のやや 日陰 に 生え 、高さ 30 〜 50 センチ 。 茎 は 四角柱 で、節に 長い 毛がある。 葉 は 卵形 で 対生 する。 4〜 6月 ごろ、 葉 の 付け根 ごとに 淡紅 紫色 または 白色 の 唇形 の花を 輪生 する。 名は、花を笠をかぶった 踊り子 に 見立て た ことによる 。 野芝麻 。 《 季 夏》「—咲

キバナオドリコソウとオドリコソウ せっかち散歩
オドリコソウ ヒメオドリコソウ 違い
オドリコソウ ヒメオドリコソウ 違い-いかりそう イキシオリリオン ウエストリンギア エレモフィラ・ニベア えんどう おおいぬのふぐり オーブリエチア オステオスペルマム オステオスペルマム おどりこそう かたくり カリブラコア きくざきいちげ きゅうりぐさ きらんそうオドリコソウ/おどりこそう/踊子草 ・北海道から九州までの広い範囲に分布するシソ科の多年草。 半日陰地を好み、山林や竹藪の縁など湿気の多い場所に大きな群落を作る。 花の様子が、編笠をかぶって踊る人に似ているとしてオドリコソウと名付けられた。 ・葉はシソに似た卵形で茎から対になってまばらに生じる。 長さは2~7センチほどで縁にはギザギザ



オドリコソウ咲く道 新宿御苑 一般財団法人国民公園協会
ゆりわさび きらんそう しょうじょう ばかま かたくり ひめ おどりこそう;おどりこそう シソ科の多年草。 山野に自生。 初夏、淡紫色または白色の唇形の花をつける。 夏 由来 「野芝麻」は漢名より。 和名は、輪生する花を輪になって踊る踊り子たちに見立てたことから。オドリコソウ(踊子草) 多年草 北海道〜九州の山野や道端の半日陰に群生する。 高さ30〜50cm。 茎はやわらかく、節に長い毛がある。 葉は対生し、長さ5〜10cmの卵状三角形〜広卵形で先端はとがる。 縁にあらい鋸歯があり、網目状の脈が目立つ。 上部の葉腋に白色〜淡紅紫色の唇形花を密に輪生する。 花冠は長さ3〜4cmで、上唇はかぶと状、下唇は3裂する。
ツルオドリコソウ/キバナオドリコソウ Lamium galeobdolon (L) L ラミウム ガレオブドロン 上の写真について 05月 山道わきの半日陰にて撮影 科名 シソ科 Labiatae 花期(一般)/花色 57月/黄色の花を咲かせる · ヒメオドリコソウは、元々ヨーロッパに自生しており、明治中ごろに日本にやってきた帰化植物だそうです。 それに対してオドリコソウとホトケノザは自生種です。 これは私の想像ですが、近年日本に入ってきたヒメオドリコソウは科学者が分類学的に毎年この時期になると、「ええーと、どっちだったっけかなあ? 」と戸惑うことが多いのが、シソ科のホトケノザとヒメオドリコソウです。 よく一緒に生えていることがあります。 シソ科の植物は葉が対生し、しかもほとんどが十字対生(2枚の葉が
踊子草 (おどりこそう) (踊花(おどりばな)、 虚無僧花(こむそうばな)) (花) 05 423 赤塚植物園 写真集(写真9枚)へ (つぼみ、花) ↓ 下へ ・紫蘇(しそ)科。 ・学名 Lamium album var barbatum Lamium オドリコソウ属 album 白い barbatum 長いひげのある Lamium(ラミウム)は、 ギリシャ語の 「laipos(のど)」が語源で、 葉の筒が長くて のど状に見えることひめおどりこそう(姫踊り子草) シソ科 学名:Lamium purpureum 05年03月14日 東京都大井埠頭 にて 花の形が,笠をかぶった踊り子の姿を思わせることから付いた名前。 関東一帯に見られる帰化植物。 葉が茎の先端になるほど紫色がかるのが特徴で、同じ踊子草 (おどりこそう) 写真集 (全景) 撮影日 : 00. 4.23 (平成12年) 撮影場所: 墨田区 向島百花園 ↓ 下へ (全景) 撮影日 : 1999. 4.17 (平成11年) 撮影場所: 板橋区 赤塚植物園 (全景) 撮影日 : 07. 4.14 (平成19年) 撮影場所: 渋谷区 千駄ヶ谷 (つぼみ) 撮影日 : 05. 4.23 (平成17年) 撮影場所: 板橋区 赤塚植物園 (花) (花) 撮影日



踊り子 が並んだ オドリコソウ 山形市野草園



オドリコソウとヒメオドリコソウ
おどりこそう茶 ・効果・効能 ・予防 強壮、腰痛、補血、生理不順、婦人病、冷え性 薬草・漢方 青汁 - 料理の食材 若芽(和え物、油炒め、おひたし) 薬草酒・薬用酒 オドリコソウ酒 入浴剤 おどりこそう季節 初夏(5月)植物季題季題 踊子草(をどりこさう/おどりこそう) 副題 踊草(をどりぐさ/おどりぐさ) 踊花(をどりばな/おどりばな)山野・路傍の半日陰に自生する。高さ30~50cmで茎は柔らかく根元から群がって直立する。姫踊子草(ひめおどりこそう)とは 縦にも横にも倍位大きさが違う 踊る阿呆に見る阿呆、みんな揃って 踊らにゃ草草 ということから 踊子草の発祥地は徳島だったわけ。 ホントかなぁ Cobucim




オドリコソウ 踊子草 3号 1ポット チャーム




ツルオドリコソウ 蔓踊子草 花と葉っぱ
踊子草おどりこそう 夏 植物 ツイート 0 シソ科の多年草。 春から初夏にかけ、淡紅または白色の花を輪状につける 一覧に戻る Sおどりこそう(踊り子草) シソ科 学名:Lamium album var barbatum 03年04月29日 小石川植物園 にて 花の色は薄赤から白色と異なるものがあるが、これはほぼ白色のオドリコソウ。 ヨーロッパ原産の ツルオドリコソウ ツルオドリコソウ は黄色の花を付ける オドリコソウ オドリコソウ · オドリコソウ(踊子草)の学名 Photo byHans オドリコソウ(踊子草)の学名 はLamium album var barbatum です。 種名のalbum(アルバム)は「白い」、小名のbarbatum(バァバツム)は「長い髭のある」、Lamium(ラミウム)は「咽喉」です。 ギリシャ語が語源になっています。 別名に、オドリバナ「踊花」・コムソウバナ「虚無僧花」の2つがあります。




オドリコソウ




オドリコソウ 踊子草 ヒメオドリコソウ 山野草に癒されて
この方も私同様少年期をすぎてしまってからの最近先生のファンになったそうな。ええと、インデックスによるとバス、郵便関係、の頁がありまして、なぜか鉄道の頁ができてないそうです。そういう系統の方はいってみるとおもしろいかも。 ( )・ ひめおどりこそう ・ ひめじょおん ・ ヒヤシンス ・ ひょうたんぼく ・ ひるがお ・ ひろっこ ・ ふきのとう ・ ふくじゅそう ・ ふじ ・ ふじばかま ・ ふたりしずか ・ ふよう ・ フリージア ・ ベゴニア ・ べにばな ・ べんけいそう ・ ポインセチアシソ科 オドリコソウ属 Lamium galeobdolon 〔基本情報〕 高さ30~50cmの多年草。 地下に匍匐枝を伸ばして広がります。 茎は直立して、断面は四角形で、下向きの短い毛がはえます。 葉は対生する単葉で、長さ5~8cmになる卵形で、粗い鋸歯があります。 花は上部の葉腋に輪散花序をなし、黄色です。 花冠は長さ15~25cmの唇形花で、上唇はかぶと状になり、縁には毛




今年出逢った山野草 21 オドリコソウ 山想花 Sansouka ブログ




キバナオドリコソウ Lamium Galeobdolon シソ科 Lamiaceae Labiatae オドリコソウ属 三河の植物観察
踊子草 (おどりこそう、をどりこさう)初夏 季語と歳時記 子季語 踊草、踊花、虚無僧花 解説 シソ科の多年草。 道端や垣根のスキ間、空き地などに群生してい る。 花の形が笠をかぶって踊る人のように見える。 花は淡紅紫色 または白で1年草(越年草 winter annual)、高さ10~30㎝。 不快な匂いがある。 わずかに毛があり、茎は4稜形、斜上する。 葉柄は細く、長さ4㎝以下。 葉身は長さ15~4㎝×幅2~5㎝(花葉はしばしば小さい)、広卵形~ほとんど腎形、不規則な深い歯(欠刻状の歯状)又キバナオドリコソウ (黄花踊子草) ヨーロッパ東部から西アジア原産のつる性多年草。 帰化植物。 葉は対生し、葉身は卵形から円形で、縁に粗い鋸歯があり、白い斑が入るものもある。 45月に葉腋から唇形の黄色の花を数個輪生し、数段つける。 花後に




オドリコソウの仲間 ラミウム シソ科



オドリコソウ Lamium Album L Var Barbatum かぎけん花図鑑
いかりそう うすばさいしん みどりうすばさいしん うすげさいしん たまのかんあおい ふたばあおい つるおどりこそう やまえんごさく new ひなそう たんぽぽ しろばなたんぽぽ かんとうたんぽぽ ふき きゅうりぐさ やくち じろぼうえんごさく すぎな ぜんまい ざぜんそうさつまいなもり きばなのあまな しろばな ねこのめ みやまはこべ むさしあぶみ;今年の藤の花は見事でした。古城公園東側のお堀越しからの眺めは まさに美しい緞帳を見ているかのようで佇みました。5月も もう後半、つぼみをたくさんつけた庭の紫陽花が雨のシャワーをもらって気持ちよさそう。今年は梅雨入りが早そうです。 2151




四季の山野草 オドリコソウ



蔓踊子草 ツルオドリコソウ 花図鑑
4~6月 全長 30~50cm 区分 多年草 説明 花形が笠をかぶった踊り子に似ていることに由来する。 上部の葉の付け根に、リング状に花をつける。 日陰の山野、道端




オドリコソウ 東北森林管理局




オドリコソウとヒメオドリコソウ 栃木県宇都宮市 国産材のハープを作り奏でる森のハープ弾きのブログ




オドリコソウ Lamium Album Var Barbatum シソ科 Lamiaceae Labiatae オドリコソウ属 三河の植物観察




オドリコソウ属




オドリコソウ



オドリコソウ エンゴサク




オドリコソウ 踊り子草 園芸種 Hayashi No Ko




尾久の原 オドリコソウとヒメオドリコソウ 東京都東部7公園




オドリコソウ 踊子草 シソ科 山野の花実



オドリコソウ 植物検索 撮れたてドットコム




キバナオドリコソウとオドリコソウ せっかち散歩



オドリコソウ ヒメオドリコソウ 山野草 植物めぐり



オドリコソウ




オドリコソウ属 Wikipedia




4月7日の花言葉 オドリコソウ 薬剤師stephenのよろずブログ 楽天ブログ




オドリコソウとは コトバンク



ヒメオドリコソウ




キバナオドリコソウとオドリコソウ せっかち散歩




オドリコソウ属 似ている 似ていない ヒメオ エバーグリーンポスト




オドリコソウ 踊子草 花姿を花笠をかぶって踊る人々にたとえて く にゃん雑記帳



Kiodoriko



オドリコソウ 踊子草 咲き始めています 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園




オドリコソウ赤白黄色 湯戯三昧 蕎麦三昧できるかな




オドリコソウ みんなの花図鑑 掲載数 3 406件



オドリコソウ 花言葉 一覧 花図鑑 花の写真 フラワーライブラリー



オドリコソウ Lamium Album Var Barbatum シソ科 オドリコソウ属 オドリコソウは北海道から九州に分布する多年生草本 朝鮮半島から中国にも分布する 地下茎で広がり 路傍や山裾 竹林 河川などに群生する 春に葉腋に輪状に花を咲かせる 花




オドリコソウの葉と花のクローズ アップ の写真素材 画像素材 Image




オドリコソウ




ヒメオドリコソウ シソ科 オドリコソウ属 越年草 なごみのとき



オドリコソウ 素人植物図鑑




ヒメオドリコソウ Wikipedia




オドリコソウ ノヂシャ 他 当尾 とうの からの風の便り




オドリコソウ



ヒメオドリコソウ 姫踊り子草 シソ科オドリコソウ属 草津温泉 草津スカイランドホテル 公式



オドリコソウ 花しらべ 花図鑑




キバナオドリコソウ 植物図鑑 エバーグリーン



花図鑑 ツルオドリコソウ キバナオドリコソウ シソ科オドリコソウ属




オドリコソウとは コトバンク



春から初夏の薬用植物 公益社団法人 相模原市薬剤師会 神奈川県 相模原市




オドリコソウ 里山の植物 サラノキの森




踊子草 オドリコソウのイラスト素材



お花の写真集 オドリコソウ 踊子草




オドリコソウ シソの仲間 ピグモンよりかなりでかい 水戸市大場町 島地区農地 水 環境保全会便り




オドリコソウ ヒメオドリコソウ ホトケノザの比較 山野草を育てる



オドリコソウ
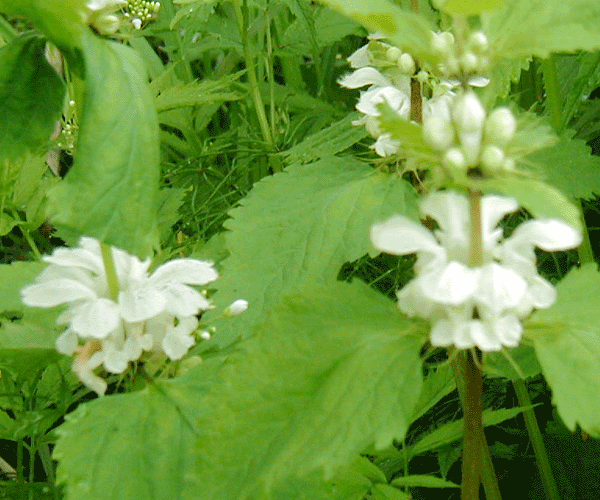



オドリコソウ 踊子草 2株 北の山菜web3号店




オドリコソウ Renaissance



オドリコソウ 踊子草



オドリコソウ咲く道 新宿御苑 一般財団法人国民公園協会




オドリコソウ 踊子草 花々のよもやま話




キバナオドリコソウ Lamium Galeobdolon シソ科 Lamiaceae Labiatae オドリコソウ属 三河の植物観察




オドリコソウ おどりこそう 踊子草 庭木図鑑 植木ペディア




踊子草 オドリコソウ と姫踊子草 ヒメオドリコソウ 自然風の自然風だより




雪の中のオドリコソウ ハチ北観光協会




オドリコソウ 踊子草 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園



ツルオドリコソウ シソ科




オドリコソウ




オドリコソウ 植物図鑑 エバーグリーン



オドリコソウ 高尾山の宝物たち Takao 599 Museum



オドリコソウ




オドリコソウ 踊子草 花々のよもやま話




オドリコソウ属の投稿画像一覧 Greensnap グリーンスナップ




オドリコソウ 踊子草




オドリコソウ おどりこそう 踊子草 庭木図鑑 植木ペディア




オドリコソウ の写真素材 イラスト素材 アマナイメージズ




四季の山野草 オドリコソウ



オドリコソウの花が咲き ヒメオドリコソウやホトケノザも賑やかな時期になった 三田のいのしし 見て歩き日記 楽天ブログ



オドリコソウ 踊子草 とヒメオドリコソウ チューメイくんの田舎ぐらし



オドリコソウ やまぶどうの徒然日記




オドリコソウ



オドリコソウ Wikipedia




東京都板橋区 赤塚植物園 オドリコソウ シソ科オドリコソウ属 多年草 北海道 九州 東アジアに分布 18 4 13 Plants White Plants Planting Flowers




踊子草 オドリコソウ



ヒメオドリコソウ 姫踊り子草 シソ科オドリコソウ属 草津温泉 草津スカイランドホテル 公式




オドリコソウ属 似ている 似ていない ヒメオ エバーグリーンポスト



キバナオドリコソウ 舎人野草園



オドリコソウ




オドリコソウ属の投稿画像一覧 Greensnap グリーンスナップ



ツルオドリコソウ




オドリコソウ 踊子草 ヒメオドリコソウ 山野草に癒されて




オドリコソウの育て方 夏は高温と加湿を避けて栽培 花と木の育て方 元気に生長させる栽培のコツ




オドリコソウの仲間 ラミウム シソ科




キバナオドリコソウ




ツルオドリコソウ 花しらべ 花図鑑



キバナオドリコソウ 素人植物図鑑




野草の花 オドリコソウ 踊子草 気楽に気ままに趣味生活



キバナオドリコソウ 植物写真鑑



コメント
コメントを投稿